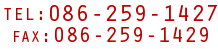電気工事士について
ビルや工場、商店や住宅などの電気設備は、その安全を守るため、工事の内容によって資格のある人でなければ
電気工事を行ってはならないことが、法律(電気工事法)で定められています。
電気工事のミスで感電や火災が起こる可能性も考えられますので、
そうならないために、きちんとした知識を持つ人が作業を行う必要があります。
その資格のある人を「電気工事士」といいます。
工事の範囲によって「第一種電気工事士」と「第二種電気工事士」の2種類があり、
都道府県知事から与えられる国家資格です。
「第二種電気工事士」は、一般住宅や店舗など600ボルト以下で受電する設備の工事に従事できる。
「第一種電気工事士」は、第二種の範囲と最大電力500キロワット未満の工場、ビルなどの工事に従事できる。
とされています。
電気工事士の試験には、受験資格制限はありません!!!第一種、第二種ともに誰でも受験できます。
受験資格は非常に幅広く、性別や国籍、年齢など関係なく誰でも受験可能です。
ただし第一種については、免状交付には一定以上の実務経験が必要です。
第二種は試験に合格すれば免状交付されますので、第二種電気工事士からの受験がオススメです。
現代の生活に電気の無い世の中は想像もできませんし、電気は必要不可欠ですよね!
それ故に電気工事の件数は多く、電気工事士は安定的に需要のあるお仕事となっています。
資格取得するなら、まずは『第二種電気工事士』から
電気工事に関する資格のなかには実務経験が必要なものもあります。
電気工事士は実務経験が必要なく、始めて資格を取得するという方でも取得要件に当てはまる場合が多くなっています。
電気の資格でも難易度の高いものは現場で重宝されるということもあり、
「資格を取るなら電気主任技術者を取りたい!」という方もいらっしゃるでしょう。
しかし初めて資格をとるという場合はまず「電気工事士」をおすすめします。
その理由は受験資格です。
まずは電気工事士の資格を取得して、それから実務経験を積むのもよいのではないでしょうか
第二種電気工事士の試験
第二種電気工事士の試験に合格するためには、「筆記試験」と「技能試験(実技試験)」の両方に合格する必要があります。
第二種電気工事士の場合、上期と下期の年2回の試験でチャンスがあります。
例年ですと、上期は6月頃、下期は10月頃が筆記試験日です。事前に申し込みが必要となります。
申込の締切は、筆記試験日の2~3ヶ月前になっていますので、早めに手続きを済ませておきましょう。
(詳しい日程は毎年変わりますので、年度ごとにご確認ください)
まずは筆記試験の対策から始めてください。
技能試験は、筆記試験当日から1~2ヶ月後の実施のため、筆記試験の後から対策を始める方が多いです。
筆記試験はテキストや過去問集などを利用しましょう。
試験対策の講座なども様々紹介されているので、一度検索してみてください。
電気の資格のなかでも、第二種電気工事士は実務経験がなくても受験することができます。
第一種は毎年筆記が10月ごろ、技能は12月ごろに行われています。
第二種は上期試験が6月ごろ、下期試験は10月ごろ行われています。
試験は全国の地区ごとに設置された会場で受けることができます。
当社では、資格取得制度が充実しており、着実に自分自身のスキルアップを目指していただけます。
未経験者大歓迎!電気工事士として一緒に働いてくれる仲間を募集しています!